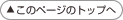会 長 挨 拶
立命館大学宮城県校友会 会長 千田芳文(S49.文)
皆様には日頃より、母校立命館と本県校友会活動に対し、熱い母校愛と深いご理解ご協力をいただいておりますことに、心から感謝申し上げます。
今年で設立以来47年目を迎えた本会の歴史を紐解きますと、1978(昭和53)年7月22日に、前身の理工学部同窓会(衣笠会)を基盤に立命館大学校友会宮城県支部として設立され、第1回総会が44名の参加者を得て、東北電力ビルの隣にあったグランドホテル仙台で開催されました。
初代の逸見英夫会長(故人)や大沼久明事務局長を始めとする設立時メンバーのご尽力で、県内の同窓生の確認や組織体制が確立され、以来、第2代下村泰雄会長、第3代大沼会長、そして4代目の私へとバトンが引き継がれ、また歴代事務局長には本部との連携や会務運営の重責を担っていただいて今日に至っています。創立時の名簿に登載されている会員数は101名でしたが、現在はその5倍以上の560名程を数え、近年特に女性会員の増加が顕著です。
半世紀近くにわたる歴史の中では、様々な活動やイベントも実施されてきましたが、特に本県校友会活動における大きな特徴として、2005(平成17)年から仙台が会場地となった全日本大学女子駅伝対校選手権大会(杜の都の大学女子駅伝)の応援・祝賀会の実施があります。
昨年度まで42回を数える同大会の中で、仙台への会場地移転を挟んで10回の優勝、そして昨年9年ぶりに11回目の優勝という輝かしい成績を母校陸上競技部の女子チームは挙げてきており、それを応援する我々にとっても、本部や他県との連携が強化されて活動に大きな弾みがつきました。
殊に、2011(平成23)年の東日本大震災の年も、母校チームはその力強い走りで優勝を成し遂げ、我々立命館関係者のみならず宮城・東北の被災地に励ましと元気を与えてくれました。
また、この震災の折には、母校と校友会本部ではいち早く被災地支援体制を立ち上げ、義捐金や震災復興ツアー等、様々な復興支援事業を長期間にわたって続けていただきました。
2018(平成30)年に仙台で開催された全国校友大会もその一環と位置付けられましょう。
面積的には日本全体の4割を占める広大な北海道・東北の8つの校友会(北海道は2つ)が、校友会本部と連携協力して開催したこの大会で、全国との絆が一段と強化されることとなりました。
そしてこれを契機に、この8校友会が持ち回りで「北海道・東北ブロック会議・交流会」を開催するようになり、開催道県の活性剤となって、特に若手や女性会員の活動参加に大変有効な役割を果たしてきています。
本会に限らず近年顕著なこととして、人の繋がりの困難化・希薄化があげられると思います。個人情報保護の関係で2003(平成15)年を最後に本会でも会員名簿発行を取りやめ、かつてのように名簿で会員同士が連絡を取り合ったり情報共有することが難しくなっていましたが、そこに更にコロナ禍が追い打ちをかけました。
様々な団体の活動の在り方や個人同士の繋がりが変化する中で、これからの時代はメールやライン、SNSといった新しいコミュニケーション手段をどう活用していくかが鍵で、本会でも連絡や情報伝達手段としてメールやホームページ等も活用して、新しいスタイルも模索しながら役員・会員のチームワーク、全国の校友とのネットワーク等の繋がりを深め、広げていくことで活性化を図って参りたいと思います。
同窓会組織や活動のポイントは、お互いの「ちょっと重なる共通項」にあると思われます。時代や、学部・学科、サークル、キャンパスなどは違っても、「青春真っただ中で同じ立命館の空気を吸っていた。」ただそれだけの共通項による絆がどれだけ深まるかでしょう。
会員皆様の積極的なご参加をお願い申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。
令和7年7月12日