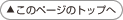白川 静(しらかわ しずか 1910年4月 – 2006年10月30日)は、漢文学者。立命館大学名誉教授。文字文化研究所所長、理事長。福井県足羽郡佐佳枝町(現在の福井市中心部)生まれ。
1923年、順化尋常小学校を卒業後、広瀬徳蔵(のちの民政党代議士)の事務所に住み込みつつ、成器商業夜間部(現大阪学芸高校)に通う。このころ、広瀬の蔵書を読み漁って漢籍に親しんでいく。
立命館大学専門部国漢科を経て、立命館中学校教諭に。その後、立命館大学法文学部漢文学科に入学。同大学予科教授となる。1954年からは立命館大学文学部教授を務めた。1976年に66歳で定年退職。1981年には名誉教授の称号を受けている。
1962年、博士論文「興の研究」で、文学博士号を取得(京都大学)。
漢字研究の第一人者として知られ、漢字学三部作『字統』(1984年)、『字訓』(1987年)、「字通」(1996年)は白川のライフワークの成果である。甲骨文字や金文といった草創期の漢字の成り立ちに於いて宗教的、呪術的なものが背景にあったと主張したが、実証が難しいこれらの要素をそのまま学説とすることは歴史学の主流からは批判された。しかし、白川によって先鞭がつけられた殷周代社会の呪術的要素の究明は、平勢隆郎ら古代中国史における呪術性を重視する研究者たちに引き継がれ、発展を遂げた。万葉集などの日本古代歌謡の呪術的背景に関しても優れた論考を行っている。
最近では、平凡社から「白川静著作集」(全12巻、完結)、「白川静著作集別巻」(全22巻、2004年現在刊行中)を刊行する傍ら、中学・高校生以上の広い読者を対象とした漢字字典「常用字解」や、インタビュー・対談などを収録した「桂東雑記」(I・II)を刊行し、活躍した。現代最後の碩学と称せられていた。
2006年10月30日、内臓疾患により死去。享年96歳。
主な著作
『金文通釈』(全7巻9冊)
『説文新義』(全16巻)
『稿本詩経研究』(全3巻)
『詩経—中国の古代歌謡』
『漢字』
『字統』
『字訓』
『字通』
『孔子伝』
受賞歴
毎日出版文化賞特別賞(1984年)
菊池寛賞(1991年)
朝日賞(1996年)
京都府文化特別功労賞(1996年)
文化功労者(1998年)
勲二等瑞宝章(1999年)
第8回井上靖文化賞(2001年)
文化勲章 (2004年)